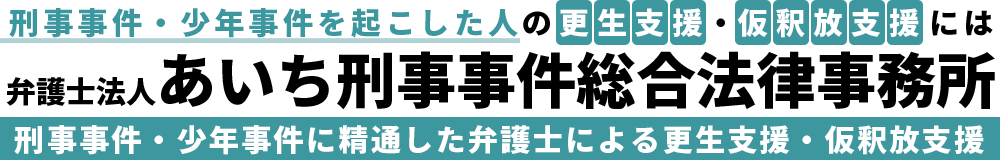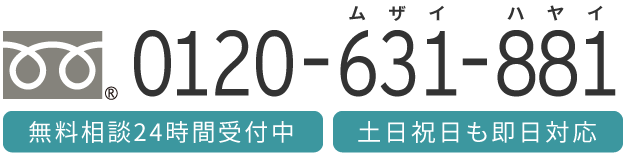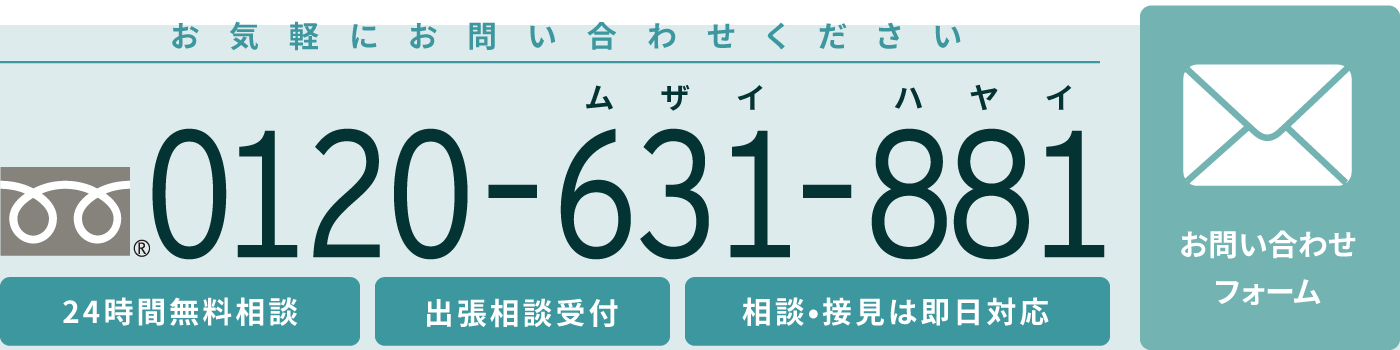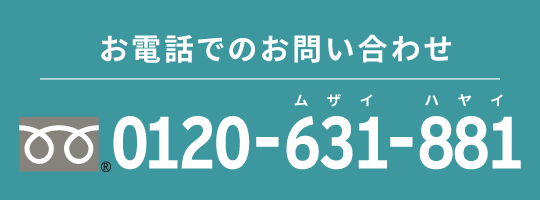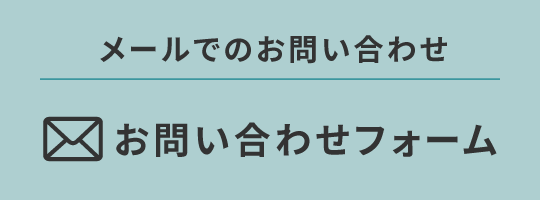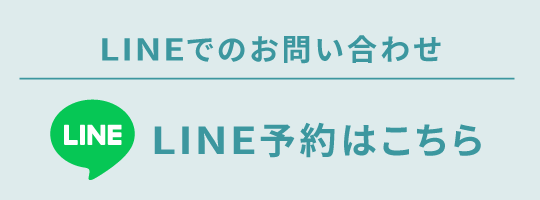刑事事件について責任能力がない、または責任能力が限定的である(完全ではない)と判断されて、起訴されなかったり、刑事施設へ収容されなかったりした人に対しては、医療観察法に基づいて、検察官から、入院や通院の申立てがなされることがあります。
入院や通院の措置は、必ずしも本人にとって有利なものとは限りませんから、刑事事件と同様に、本人のために弁護士を依頼することができます。
医療観察法の場合、弁護士は、「付添人」という呼ばれ方をします。
医療観察法に基づく申立てがあった時に、弁護士が付添人としてできる活動の例について解説します。
このページの目次
申立てがあった事実について争いがある場合
まず、前提となる事実について争いがある場合には、事実についてしっかりと主張するべきです。
特に、裁判になる前に申立てがなされたような場合、例えば、検察官が不起訴処分にしたものの入院する必要はあると考えて医療観察法の申立てをしたというような場合です。
このような場合では、裁判所での厳格な手続きによって証拠が取調べられたり、事実の認定が行われたりしたわけではありませんから、そもそも「自分は犯人ではない」という主張の場合もあります。
審判の場でも、入院や通院措置の前提となる事実については審理の対象となりますから、争いがある場合には弁護士に依頼して、きちんと主張を行うべきです。
心神喪失、心神耗弱と思われる人が、自分のために弁護士を活用することは難しいかもしれませんから、そのような場合にはご家族や周りの方が弁護士につなげてあげる必要もあるでしょう。
通院や入院に適した状態であるかどうか
入院や通院が決定されるのは、医療が必要な状態であってかつ、治療が可能であり、治療によって社会復帰が促進されるという場合のことを言います。
そのため、疾病の状況や周囲の環境(家族の状況やそれまで通っていたかかりつけ医の受け入れ状況)によっては、強制的な措置ではなく、任意での入院や通院を続けた方が良い場合もあり得ます。
付添人として、本人の家族や主治医、福祉の方々と連携し、本人が社会で生活していく余地がないのかという点を追求していく活動が重要でしょう。
不服の申立て
入院や通院の措置が決定された場合、その決定は本人にとっても不利益なものになりますから、不服の申立てをすることができます。
刑事事件における控訴のようなものです。
この不服申し立ては、抗告と呼ばれます。抗告審では、基本的に書面の審査で終了してしまいます。
医療観察法に基づいた決定ですので、それに対する不服の申立てについても、「通院や入院の措置の決定が、医療観察法や憲法に反している」という主張をしなければなりません。
やみくもな抗告では歯牙にかからないで棄却されてしまいます。
適法な申立てとするためにも、不服申立て(抗告)については弁護士に依頼された方が良いでしょう。
入院後の申立てについて
入院した後は、時期に関わらず、いつでも退院の申立てをすることができます。
これも付添人弁護士などが代理人として行うことができます。
退院の申立てに対して、実際に退院が認められるかどうかは、その時々の状況次第で「もう入院して治療を行う必要がない」と言えるかどうかに関わってきます。
ご本人からの「退院したい」という訴えと、その周囲を取り巻く状況を、正確に聴取した上で退院の申立てについても行うべきです。
ご本人の訴えだけでは、どうしても「入院している環境がつらいから退院させてほしい」というだけのものになりがちですが、それだけでは裁判所としても退院を認められません。
もちろん、本人の「辛い」という状況は無視できないものですが、残念ながら、医療観察法上、入院を続けるか/退院を認めるか、ということの基準は、「本人の辛さ」以外の部分にも置かれています。
退院したいという訴えを、法律論に適切に転換していくためにも、代理人弁護士が就いていることが重要になるでしょう。