Archive for the ‘刑事手続一般’ Category
執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します③
執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します③

【事例】
Aさんは、大阪府岸和田市に住む30代の女性です。
Aさんは、20代の頃から仕事でストレスを感じると万引きを繰り返してしまっており、何度か警察に捕まって罰金刑を受けたこともありました。
それにもかかわらず、Aさんは万引きを繰り返してしまい、今回、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されることになってしまいました。
裁判官から判決を言い渡される際にも、次に犯罪をしたら長期間刑務所に行くことになる可能性が高いという趣旨の話をされています。
その一方で、インターネットで調べると、再度の執行猶予という制度があることも知りました。
Aさんは、二度と犯罪はしないと思っていますので、執行猶予が取り消されるかもしれないという心配はする必要がないと思っています。
ただ、どのような場合に執行猶予の判決が取り消されるのかは気になってしまいました。
その一方で、Aさんの両親は、Aさんが現に繰り返してきていますから、このままではまた繰り返してしまうのではないかと心配しています。
そこで、万が一にも執行猶予が取り消されるようなことがないように、Aさんのためにできることはしておきたいと考えています。
Aさんと両親は、更生支援にも取り組んでいるということをインターネットで知り、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(事例はフィクションです)
1 はじめに
前回の記事では、Aさんや両親の疑問について解説していく前提として、執行猶予とできる条件は何かを解説してきました。
今回の記事では、その続きと、執行猶予の期間や執行猶予のバリエーションとして保護観察について解説していきます。
2 執行猶予とできる条件:「情状により」
前回の記事では、一度、拘禁刑の執行猶予の判決を受けた人であっても、取り消されることなく執行猶予の期間を満了すれば、仮にまた犯罪行為をしてしまったとしても、執行猶予となる可能性がある点を解説しました。
ただ、この場合に執行猶予となるハードルは低いものではありません。
執行猶予には、前回までに解説した条件のほかにも「情状により」執行猶予にできるのだという条件もあります。
例えば、Aさんが、1年の拘禁刑、3年間その執行を猶予するという判決を受けていたとします。
Aさんが3年間の執行猶予期間経過後に、何か新たに犯罪をしてしまったとしても、今一度執行猶予となる可能性はあります。
しかし、その新たにした犯罪がなにか、どのような理由でしてしまったのかなどといった「情状」の面で、執行猶予とはしないと判断されるかもしれないのです。
特に新たな犯罪がこれまでと同じ万引きであれば、執行猶予となるハードルはより一層高いものになるでしょう。
3 執行猶予の期間
執行猶予の期間としては、「裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間」と定められています(刑法25条1項本文)。
この期間の中で、裁判官が妥当だと思う期間を設定することになります。
ただ、何年何か月などとは定めずに、年単位で設定することがほとんどです。
4 保護観察
また、執行猶予の期間中に「保護観察に付する」という決定をすることもできます(刑法25条の2第1項)。
保護観察に付されると、保護観察所のもと、様々な条件を守りながら生活する必要があります(更生保護法50条、51条等)。
保護観察に付された場合にはその条件に違反することで執行猶予が取り消されてしまう可能性があります。
次回の記事では、執行猶予の取消しについて解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判での弁護活動や警察の捜査を受けている段階での弁護活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、事件を起こしてしまった方の刑事手続きが終了した後、判決を受けた後についても顧問弁護士として事件を起こされた方の更生やご家族の不安に寄り添いながらサポートさせていただきます。
今後の再犯防止に不安のある方や実刑判決を受けてしまい仮釈放やその後の社会復帰に不安を抱えた方は是非一度相談してみてください。更生支援に豊富な経験を持つ弁護士が初回無料で相談対応をさせていただきます。
再犯防止や真の更生に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します②
執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します②
【事例】
Aさんは、大阪府岸和田市に住む30代の女性です。
Aさんは、20代の頃から仕事でストレスを感じると万引きを繰り返してしまっており、何度か警察に捕まって罰金刑を受けたこともありました。
それにもかかわらず、Aさんは万引きを繰り返してしまい、今回、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されることになってしまいました。
裁判官から判決を言い渡される際にも、次に犯罪をしたら長期間刑務所に行くことになる可能性が高いという趣旨の話をされています。
その一方で、インターネットで調べると、再度の執行猶予という制度があることも知りました。
Aさんは、二度と犯罪はしないと思っていますので、執行猶予が取り消されるかもしれないという心配はする必要がないと思っています。
ただ、どのような場合に執行猶予の判決が取り消されるのかは気になってしまいました。
その一方で、Aさんの両親は、Aさんが現に繰り返してきていますから、このままではまた繰り返してしまうのではないかと心配しています。
そこで、万が一にも執行猶予が取り消されるようなことがないように、Aさんのためにできることはしておきたいと考えています。
Aさんと両親は、更生支援にも取り組んでいるということをインターネットで知り、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(事例はフィクションです)
1 はじめに
前回の記事では、Aさんや両親の疑問について解説していく前提として、そもそもAさんが言い渡されたような執行猶予とはなにか、執行猶予とできる条件は何かを解説してきました。
今回の記事では、執行猶予とできる条件について、その続きを解説していきます。
2 執行猶予とできる条件:対象者
前回の記事では、「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と、拘禁刑については3年、罰金刑については50万円と、執行猶予とすることができる上限が定められていることを見てきました。
しかし、条件はこれだけではありません。
刑法25条1項によると、次のどちらかに当たる人でないと、執行猶予とはできないことになります。
①「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(1号)
②「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(2号)
①は、これまでに拘禁刑以上の刑、つまり死刑の判決や拘禁刑の判決(執行猶予とされた場合も含みます。)を受けたことがない人が対象だということです。
②は、例えば一度、実刑の判決を受けた人であっても、その実刑の期間が終わってから(仮釈放となった日からではありません。)、5年経過していれば、対象に含むことができるなどという意味です。
ここで問題となるのは、執行猶予の期間が満了した人はどうなるかという点です。
途中で執行猶予を取り消されることなく、執行猶予の期間である3年が満了すると、その効果として「刑の言渡しは、効力を失う」と定められています(刑法27条1項)。
この効果により、再び「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(1号)に該当することになりますから、仮にまた犯罪行為をしてしまっても、執行猶予となる可能性も出てくるのです。
次回の記事では、今回の続きや執行猶予の期間について解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判での弁護活動や警察の捜査を受けている段階での弁護活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には、事件を起こしてしまった方の刑事手続きが終了した後、判決を受けた後についても顧問弁護士として事件を起こされた方の更生やご家族の不安に寄り添いながらサポートさせていただきます。
今後の再犯防止に不安のある方や実刑判決を受けてしまい仮釈放やその後の社会復帰に不安を抱えた方は是非一度相談してみてください。更生支援の豊富な経験を持つ弁護士が初回無料で相談対応をさせていただきます。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します①
執行猶予の制度と執行猶予の取消しについて刑事事件少年事件に精通した弁護士が解説します①

【事例】
Aさんは、大阪府岸和田市に住む30代の女性です。
Aさんは、20代の頃から仕事でストレスを感じると万引きを繰り返してしまっており、何度か警察に捕まって罰金刑を受けたこともありました。
それにもかかわらず、Aさんは万引きを繰り返してしまい、今回、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されることになってしまいました。
裁判官から判決を言い渡される際にも、次に犯罪をしたら長期間刑務所に行くことになる可能性が高いという趣旨の話をされています。
その一方で、インターネットで調べると、再度の執行猶予という制度があることも知りました。
Aさんは、二度と犯罪はしないと思っていますので、執行猶予が取り消されるかもしれないという心配はする必要がないと思っています。
ただ、どのような場合に執行猶予の判決が取り消されるのかは気になってしまいました。
その一方で、Aさんの両親は、Aさんが現に繰り返してきていますから、このままではまた繰り返してしまうのではないかと心配しています。
そこで、万が一にも執行猶予が取り消されるようなことがないように、Aさんのためにできることはしておきたいと考えています。
Aさんと両親は、更生支援にも取り組んでいるということをインターネットで知り、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に行くことにしました。
(事例はフィクションです)
1 はじめに
Aさんや両親の疑問について解説していく前提として、まず今回の記事では、Aさんが言い渡されたような執行猶予とはそもそも何かについて解説していきます。
2 執行猶予とは
一般的に、単に執行猶予というときには、刑法25条1項に定められている制度のことを指すことが多いです。
この執行猶予というのは、刑の言渡しはするけれども、その刑の執行は一定期間猶予し、その猶予する期間を刑事裁判を受けることなく経過したときには、刑罰権を消滅させることとする制度をいうとされています。
ここでいう「刑の執行」というのは、刑を言い渡した判決が確定したときに、その判決の内容を実現させることをいいます。
つまり、拘禁刑を例にいえば、拘禁刑の執行とは実際に刑事施設に収容することとなります。
今回、Aさんが1年の拘禁刑で、その執行を3年間猶予するという判決を受けていたとします。
その場合、1年の拘禁刑だという刑の言渡しはするが、この1年の拘禁刑という刑を執行して、実際に刑事施設に収容することは、3年間という一定期間猶予し、この3年間を無事に経過すれば、この1年の拘禁刑を受けさせるという刑罰権は消滅するという意味だということになります。
3 執行猶予とできる条件
執行猶予がどのようなものか見てきましたが、どのような場合に執行猶予とできるでしょうか。
刑法25条1項の本文を見ると、まず、「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」と書かれています。
つまり、拘禁刑については3年、罰金刑については50万円と、執行猶予とすることができる上限が定められているのです。
また、拘禁刑だけではなく、罰金刑についても執行猶予とすることができるというのも、あまり知られていないのではないでしょうか。
もっとも、実際には罰金刑に執行猶予が付されることはほとんどないように思われます。
次回の記事では、この続きから解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判での弁護活動や警察の捜査を受けている段階での弁護活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
具体的には更生支援に向けた見守り弁護士活動、顧問弁護士活動を行っています。不良交友関係からの脱却や再犯防止に向けた課題の実施やアドバイスなど更生に向けた積極的な弁護活動を行っています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件と管轄する機関について少年事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します②

【事例】
Aさんは、福岡県春日市の実家に両親と兄の4人で住む17歳の高校生です。
Aさんは、同世代の人がSNSで羽振りの良い生活をアップしている投稿を見て、自分も同じような生活をしたいと考えるようになってしまいました。
そのような中で、SNSで高額のアルバイトを募集しているという投稿を見つけたので、Aさんは連絡を取って応募してしまいました。
Aさんが応募したのはいわゆる闇バイトで、行ったことの内容も、指示役の指示に従って被害者の家に行き、指示役の指示のとおりに被害者のキャッシュカードを騙し取るというものでした。
Aさんは福岡県内だけではなく、東は東京や名古屋、南は熊本や鹿児島でも同様のことを指示されて行っていました。
Aさんが、このように犯罪に手を染めてから1ヶ月ほどが経過したある日、警察官が春日市の自宅にやってきました。
そして、そのまま警察官に逮捕されてしまったのです。
しかもその警察官は、東京の警察官だったのです。
逮捕しに来たのは東京の警察官ですから、Aさんはその日のうちに東京に連れて行かれて、東京の警察署で身体拘束されることになりました。
Aさんがしたことを警察官から聞いた両親は、身体拘束されるのは仕方ないと思いつつも、このままずっと東京で身体拘束されるのだろうかということに強い不安を感じていました。
そこで、Aさんの両親は、あいち刑事事件総合法律事務所に連絡を取り、初回接見を利用して弁護士にAさんとの面会を依頼し、面会をした弁護士にこのことを相談することにしました。
(事例はフィクションです)
1 はじめに
昨今、特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)など犯罪地が広域にわたる場合がありますが、前回の記事では、その場合に警察はどこの警察が動くのか、どこの裁判所が担当するのかという点について、解説してきました。
具体的には、まずは東京の警察がこのまま動き、別の都道府県の警察(例えば熊本なら熊本)が逮捕しにくる(再逮捕)可能性もあるという内容でした。
今回は、どこの裁判所が担当するかという点について解説していきます。
2 担当する裁判所
今回のAさんのように、捜査の段階で身体拘束される場合は、事件を捜査している警察がある都道府県の警察署などに拘束されることがほとんどです。
そして、捜査を終えると事件は家庭裁判所に送られることになります(家庭裁判所送致)。
送致先の裁判所は、事件を捜査している警察署、検察庁に対応する家庭裁判所となります。
例えば、東京都の新宿警察署、東京地方検察庁が捜査をしていた場合、東京家庭裁判所が送致先となりますし、熊本県の熊本中央警察署、熊本地方検察庁が捜査をしていた場合、熊本家庭裁判所が送致先となります。
しかし、一旦は捜査している警察署、検察庁に対応する家庭裁判所に送致されても、その後にその少年の住んでいる場所に対応する家庭裁判所に移送されることが多いです。
つまり、Aさんの場合も、一旦は東京家庭裁判所や熊本家庭裁判所に送致されたとしても、住所地である春日市を管轄している福岡家庭裁判所に移送される可能性が高いといえます。
そのため、捜査の段階では各地で身体拘束される可能性が高いですが、家庭裁判所に送致された後には、福岡県に戻ってくる可能性が高いのです。
もっとも、各地の少年鑑別所から福岡県の少年鑑別所に実際にAさんが移動してくるまでには数日はタイムラグがあることも多いです。
福岡の家庭裁判所に移ったとの連絡が来たとしても、直ぐに福岡の少年鑑別所で面会できるとは限りませんので、家庭裁判所や少年鑑別所からの通知をよく確認する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件が進行している段階での処分や身体拘束に向けた活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件と管轄する機関について少年事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します①
【事例】
Aさんは、福岡県春日市の実家に両親と兄の4人で住む17歳の高校生です。
Aさんは、同世代の人がSNSで羽振りの良い生活をアップしている投稿を見て、自分も同じような生活をしたいと考えるようになってしまいました。
そのような中で、SNSで高額のアルバイトを募集しているという投稿を見つけたので、Aさんは連絡を取って応募してしまいました。
Aさんが応募したのはいわゆる闇バイトで、行ったことの内容も、指示役の指示に従って被害者の家に行き、指示役の指示のとおりに被害者のキャッシュカードを騙し取るというものでした。
Aさんは福岡県内だけではなく、東は東京や名古屋、南は熊本や鹿児島でも同様のことを指示されて行っていました。
Aさんが、このように犯罪に手を染めてから1ヶ月ほどが経過したある日、警察官が春日市の自宅にやってきました。そして、そのまま警察官に逮捕されてしまったのです。
しかもその警察官は、東京の警察官だったのです。
逮捕しに来たのは東京の警察官ですから、Aさんはその日のうちに東京に連れて行かれて、東京の警察署で身体拘束されることになりました。
Aさんがしたことを警察官から聞いた両親は、身体拘束されるのは仕方ないと思いつつも、このままずっと東京で身体拘束されるのだろうかということに強い不安を感じていました。
そこで、Aさんの両親は、あいち刑事事件総合法律事務所に連絡を取り、初回接見を利用して弁護士にAさんとの面会を依頼し、面会をした弁護士にこのことを相談することにしました。
(事例はフィクションです)
1 はじめに
昨今、インターネットやSNSの発展、交通網の整備などからか、犯罪が広域化している印象があります。そのような傾向の中で、特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)なども広がり、闇バイトなどと称して、未成年者も含めた若年者が特殊詐欺に加担する事例も多く目にします。
問題は、犯罪地が広域にわたる場合に、警察はどこの警察が動くのか、どこの裁判所が担当するのかという点です。
特に家族が本人の更生に向けた活動をしようにも、遠方では本人への面会など十分な活動ができない可能性もありますので、身体拘束がどこでされるのかは大切になってくる場合があります。
2 少年事件の手続きの流れ
Aさんの場合、年齢が20歳未満ですから、少年事件として手続きが進んでいきます。
Aさんのように逮捕され、その後も最後まで身体拘束が続いた事件を例に、ごくごく簡単に少年事件の手続きを説明します。
まず、警察が逮捕をし、その後も身体拘束を続けるためには、検察官や裁判官の判断を経て、勾留などという逮捕とは別の決定が必要になります。
勾留中に捜査がされていき、勾留期間を終えるまでに、事件を家庭裁判所に送致することになります。
家庭裁判所に送致されてからは、少年鑑別所で拘束されながら、家庭裁判所の調査官の面接を受けるなどといった調査を受けることになります。
そのような調査を経て、少年審判を受け、処分が決まることになります。
3 担当する警察署
今回のAさんの場合、東京で起こした事件について警察が捜査をし、犯人がAさんだと辿り着いて逮捕しに来たのでしょう。
問題は、Aさんが、東京以外にも名古屋や熊本、鹿児島などでも別の事件を起こしている点です。
このような場合、基本的には名古屋なら名古屋の、熊本なら熊本の、鹿児島なら鹿児島の警察が動くことが多いです。
そのため、東京の事件について東京の警察が行った捜査が終わった後に、例えば熊本の事件で熊本の警察が逮捕しにくる(再逮捕)可能性もあるわけです。
そのため、東京の事件を捜査されている間は東京で身体拘束されることになりますし、東京の事件の捜査が終わっても、別の都道府県の警察が逮捕に来るかもしれませんから、当面の間、福岡県には戻ってこられない可能性があります。
次回の記事では、裁判所の段階について解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は北は札幌から南は博多まで全国に合計12拠点を有する大規模な事務所です。事例のように複数の警察署で捜査されるような事件であっても、各支部の弁護士が対応することでスムーズに引継ぎを行い、充実した弁護活動を受けることが可能になります。
さらに少年事件が進行している段階での処分や身体拘束に向けた活動はもとより、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
医療観察法上の手続きについて更生支援に精通したあいち刑事兼総合法律事務所の弁護士が解説します②
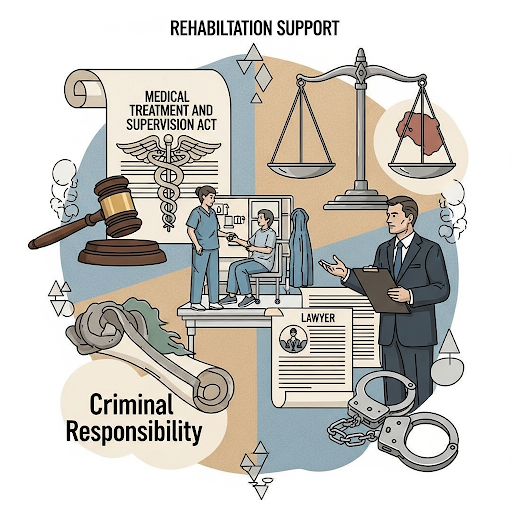
【事例】
Aさんは、佐賀県鳥栖市で60代の両親と一緒に住む40歳の男性です。
以前からAさんは精神科に通院しており、統合失調症であるという診断を受けていました。
これまでは家族に支えられながら日常生活を営んできたAさんでしたが、あるときから統合失調症の影響で幻覚や幻聴に悩まされるようになってしまいました。
その幻覚や幻聴は、「毎朝自宅に新聞を届けに来る新聞配達員は自分たち家族の命を狙っている」、「このままでは自分や家族の命が危ない」といったものでした。
このような幻聴と幻聴に囚われたAさんは、ある日、朝刊の配達に来た新聞配達員にカッターナイフで切りかかってしまいました。
異変を感じて駆け付けた人々がAさんを取り押さえたため、新聞配達員は怪我を負ったものの、命に別状はありませんでした。
その後、駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
逮捕されたAさんは警察の取調べを受けるとともに、Aさんに刑事責任を問えるのか判断するため、医師の鑑定も受けることになりました。
Aさんの家族は、Aさんの弁護人である弁護士から、担当の検察官は、医師の鑑定の結果を踏まえて、Aさんには刑事責任を問えないと判断して不起訴とする予定だと聞かされました。
もっとも、今後は医療観察法の手続きを受けることにもなるとも伝えられました。
Aさんの家族は、これからAさんがどのような手続きを受けるのか、Aさんが家に帰ってくることができるのかなどが心配となり、担当の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回の記事では、Aさんが受けることになる医療観察法の手続きを説明する前提として、なぜAさんに刑事責任を問えないと検察官が判断したのだと思われるのかについて解説してきました。
今回の記事では、どのような事件が、医療観察法(正式名称は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といいます。)の手続きの対象になるのかを解説していきます。
2 手続きの対象
医療観察法は、「継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること」を目的としている法律です(医療観察法1条)。
しかし、医療観察法は、どのような事件であっても手続きの対象となるわけではありません。
問題となっている事件がどのような事件か(行ったのが対象となる行為か)という点と、問題となっている事件がどのような処分になったかという点の2つから判断されます。
3 対象行為
医療観察法が対象としているのは、次のいずれかに該当する行為を行っている場合に限られています(医療観察法2条1項)。
⑴ 放火関係(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪またはこれらの未遂罪)
⑵ わいせつ関係(不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、監護者わいせつ及び監護者性交等罪またはこれらの未遂罪)
⑶ 殺人関係(殺人罪、自殺関与及び同意殺人罪またはそれらの未遂罪)
⑷ 傷害罪
⑸ 強盗関係(強盗罪、事後強盗罪又はそれらの未遂罪)
ここで注意が必要なのは、例えば強盗関係は、問題となっている事件が強盗事件や事後強盗事件(とそれらの未遂)だけが対象で、強盗致傷事件や強盗殺人事件などが対象外だというわけではないということです。
次回の記事では、この詳細について解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、刑事事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
また本件のように、責任能力が問題になるケースで逮捕された方については初回接見サービスをご利用をおすすめしています。責任能力が問題になる売る方の弁護活動についてきましてはこちらのページも参考にしてください。
再犯防止に向けた弁護士のサポートや責任能力が問題になりうる方の弁護活動にご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
医療観察法上の手続きについて更生支援に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します①
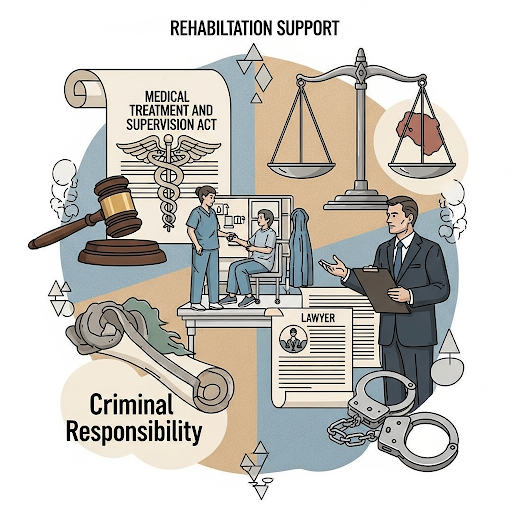
【事例】
Aさんは、佐賀県鳥栖市で60代の両親と一緒に住む40歳の男性です。
以前からAさんは精神科に通院しており、統合失調症であるという診断を受けていました。
これまでは家族に支えられながら日常生活を営んできたAさんでしたが、あるときから統合失調症の影響で幻覚や幻聴に悩まされるようになってしまいました。
その幻覚や幻聴は、「毎朝自宅に新聞を届けに来る新聞配達員は自分たち家族の命を狙っている」、「このままでは自分や家族の命が危ない」といったものでした。
このような幻聴と幻聴に囚われたAさんは、ある日、朝刊の配達に来た新聞配達員にカッターナイフで切りかかってしまいました。
異変を感じて駆け付けた人々がAさんを取り押さえたため、新聞配達員は怪我を負ったものの、命に別状はありませんでした。
その後、駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
逮捕されたAさんは警察の取調べを受けるとともに、Aさんに刑事責任を問えるのか判断するため、医師の鑑定も受けることになりました。
Aさんの家族は、Aさんの弁護人である弁護士から、担当の検察官は、医師の鑑定の結果を踏まえて、Aさんには刑事責任を問えないと判断して不起訴とする予定だと聞かされました。
もっとも、今後は医療観察法の手続きを受けることにもなるとも伝えられました。
Aさんの家族は、これからAさんがどのような手続きを受けるのか、Aさんが家に帰ってくることができるのかなどが心配となり、担当の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
今回の記事では、Aさんがどのような手続きを受けることになるのか、医療観察法の手続きとはどのようなものなのかを説明するために、その前提として、まずはAさんに刑事責任を問えない理由を解説していきます。
2 責任能力とは
ある人が行った行為を、犯罪であるとして刑罰を科すためにはいくつか条件があります。
その一つが責任能力です。
責任能力というのは、ある行為を行った人を非難するために、その行為を行った人に必要とされる一定の能力です。
このような責任能力がない場合としては、心神喪失(刑法39条1項)と言われる場合と、刑事未成年の場合があります。
刑事未成年というのは、14歳未満であることです(刑法41条)。
このいずれかに該当するのであれば、例え人を殴った、人の物を盗んだといった犯罪に当たりうる行為をしていたとしても、責任能力がないため、犯罪とはなりません。
3 心神喪失とは
それでは、心神喪失とはどのような場合でしょうか。
これは、ごく簡単に表現すると、精神の障害(病気など)により、自分の行為がしていい行為かどうか、良い行為か悪い行為かを判断する能力か、その判断に基づいて自分の行動をコントロールする能力のいずれかが全くない状態を指します。
これに対して、こういった能力が全くないわけではないが、著しく減退した状態を心神耗弱(刑法39条2項)といいますが、この場合は(限定的ではあるけれども)責任能力はあるので、犯罪は成立することになります。
Aさんの場合は、担当の検察官はAさんの刑事責任を問えないと判断していますので、医師の鑑定の結果などを踏まえて、Aさんは心神喪失であったと判断したのでしょう。
そのため、刑事裁判にはかけられませんから、不起訴と判断したものと思われます。
次回の記事では、医療観察法の手続きについて解説していきます。
責任能力が問題となりうる事件で逮捕された場合、発達障害などの診断を受けている方が刑事事件を起こし逮捕された場合には、まずは弁護士を留置先の警察署に派遣する初回接見サービスの利用をおすすめします。責任能力が問題になる場合の弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、刑事事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑法改正に伴って導入された拘禁刑について刑事事件に精通した弁護士が解説します⑧
これまで拘禁刑の導入に伴ってどのように法制度や刑事施設での処遇が変わるかについて詳しく解説してきました。
最終回である今回の記事では拘禁刑の導入に伴い弁護活動や弁護士の果たすべき活動にはどのような変化があるのかについて解説させていただきます。
具体的には、以下のような3点で弁護人の役割や弁護活動が変わってくることが予想されます。
1 量刑判断における主張の幅の拡大
拘禁刑の導入により、裁判官が量刑を決定する際に考慮する事情が広がる可能性があります。
刑務所内でも治療プログラムが導入され再犯防止に力が入れられる方針となったことで、単に専門的プログラムを受けさせるために執行猶予を付すべきと主張するのみでは、裁判所が再犯防止プログラムであれば刑務所でも受けられるのではないかと考えるようになるかもしれません。
そこで再犯防止のために執行猶予を付すべき(実刑にするべきではない)という主張をする際には、単に専門機関に通うというだけではなく何故その機関に通う必要があるのかについてより説得的な主張が求められるようになるでしょう。
また実刑となる可能性が高い件でも弁護人としては、被告人の背景事情を丁寧に調査し、処遇に関する意見を述べることが被告人にとって有利になるかもしれません。
「なぜこの被告人には刑の一部に教育的処遇が必要か」「治療プログラムの導入が再犯防止に資するか」など、量刑や処遇内容に関する説得力ある意見を提出することで処遇内容に反映される可能性もあります。
2 受刑後の処遇を見据えた弁護活動
従来の弁護活動では、主として無罪の獲得や刑の減軽を目的とした活動が中心でしたが、拘禁刑導入後は「刑の執行内容そのもの」にまで目を向けた活動が必要となります。
特に、被告人がどのような処遇分類にあたるかによって、その後の刑務所での生活や社会復帰の難易度が大きく変わる可能性があるため、受刑後の環境整備や処遇プログラムの選択にも関与することが重要です。
そのためには、社会復帰支援や家族・地域とのつながりの構築、医療や福祉との連携など、弁護人の活動範囲がこれまで以上に広がることになります。
具体的には、受刑後にも定期定期に面談や手紙などで連絡を取り合い、必要があれば処遇の改善やプログラムの実施などについて本人に代わって刑務所長などに申し入れをすることが必要になるかもしれません。
3 仮釈放・社会内処遇への意識強化
拘禁刑導入後には、従来よりも処遇の多様化が図られることから、仮釈放や社会内処遇(保護観察付き仮出所など)を前提とした支援がより重視されるようになります。
弁護人としては、判決後も被告人の処遇状況をフォローし、仮釈放申出に必要な資料や意見書を準備するなど、継続的な支援を行う体制が求められます。
まだ拘禁刑を受けた人の事例がないので不透明なところはありますが、拘禁刑の導入により再犯防止や社会復帰を重視するようになった現在では環境整備が十分になされれば、以前よりも早期に仮釈放が認められるようになるかもしれません。
また、裁判時点から仮釈放を見据えて、社会復帰の準備状況(家族の支援、住居、就労先など)を整えておくことが、処遇の選定や仮釈放の判断にプラスの影響を与える可能性があります。
このためが見込まれる場合でも、仮釈放後の社会復帰も見据えた主張をすることで早期の仮釈放に考慮される場面が増えるかもしれません。
4 まとめ
以上のように拘禁刑導入に伴い、刑罰は受けて終わりというだけでなくその後の社会復帰後世まで見据えた制度設計となり、刑罰の趣旨が変容しているといえます。
当然それに伴い弁護活動においても社会復帰や更生まで見据えた活動が求められるようになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では拘禁刑が導入される以前から、仮釈放支援や見守り弁護士(ホームロイヤー)といった活動により事件を起こされた方の真の更生や早期の仮釈放・社会復帰に向けた支援を行ってきました。
拘禁刑導入に伴いそれらの活動はさらに重要なものとなっていますので、更生支援、早期の社会復帰に向けて不安や心配がある方は是非あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
私たちは、事件の当事者となった方お一人おひとりの特性を踏まえ、社会復帰に向けた最適な支援ができるよう尽力してまいります。
刑法改正に伴って導入された拘禁刑について刑事事件に精通した弁護士が解説します⑦
1 はじめに
前回の記事では拘禁刑の導入に伴う刑事施設の役割や刑務官の役割の変化について解説しましたが、今回の記事ではそのように拘禁刑の導入に伴って変化が予定されている中で実際の現場において、そのような施設環境の改善が予定されているのか、刑務官の負担はどうなるのかという課題について詳しく解説させていただきます。
2 刑事施設の施設環境の改善について
拘禁刑の導入に向けて施設環境の改善も取り組まれています。再犯防止プログラムや職業訓練を効果的に行うには、教室や作業場、カウンセリング室など適切な設備・空間が必要です。
近年新設・改修された刑務所では、従来の雑居房・独居房だけでなく、教育プログラム用の教室や図書室、コンピュータ室などが整備されてきています。
たとえば民間活力を導入した「社会復帰促進センター」(島根あさひ、美祢、喜連川など)では、職業訓練施設や生活指導棟を備え、開放的な雰囲気の中で受刑者の自主性を伸ばす運営がなされています。
こうした先進的施設で培われたノウハウが、全国の刑務所に波及しつつあります。
たとえば喜連川社会復帰促進センターで実施されたVR職業体験のように、最新技術を活用した訓練や企業と連携した就労プログラムが他の刑務所でも導入される可能性があります(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00074.html)。
今後は老朽化した施設の改修に際しても、更生プログラム重視の視点で環境を整備していくことが求められるでしょう。
施設面の変化だけでなくそこで服役する受刑者の作業・教育機会の拡充も運営面の重要なポイントです。
拘禁刑では「作業を課すかどうか」自体を個別判断しますが、基本的には大多数の受刑者が何らかの作業に従事しつつ指導プログラムも受ける形になることが予定されています。
そのため、刑務所内で提供する作業種目や教育プログラムの種類を増やし、多様なニーズに応えられるようにする必要があります。
従来からある刑務作業(印刷、家具製作、農作業など)に加え、IT技能習得や介護実習など社会のニーズに即した新分野の訓練を取り入れる余地も検討されています。
受刑者の高齢化に対応した軽作業やリハビリ運動、逆に若年者向けの高度技能訓練プログラムなど、「作業=懲役」から「作業=職業訓練・社会貢献」へと性質が変化していくと考えられます。
その結果、受刑者は刑務所内で取得した資格や職歴を持って社会に復帰でき、刑務所も一種の「職業訓練校」「更生教育施設」としての色彩を強めるでしょう。
3 予想される現場の負担の増大について
これらの変化を実現するには、現場の負担も増大します。
職員の増員や予算措置など越えるべき課題もありますが、専門家は「受刑者の自発性・自立性を尊重した改善更生の理念を運用の中で決して見失わないことが重要だ」と指摘しています。
せっかく制度を変えても、旧来型の画一的処遇に逆戻りしては意味がありません。今後の運用を監視し、必要に応じて軌道修正していくことも求められます。
拘禁刑の導入によって刑務所は「刑を執行する場」から「再出発の準備をする場」へと変わりつつあります。その理念に沿った刑務所運営の定着こそが、真の再犯防止と安全な社会の実現に繋がると言えるでしょう。
4 今後に向けて
既に拘禁刑を定めた改正刑法が施行されましたが、実際に被告人が拘禁刑を受けるのは令和7年6月1日以降に犯した罪により裁判を受ける場合になります。
したがって裁判の期間等を考慮すれば実際に被告人に対し拘禁刑が宣告されるのは早くても施行から2,3か月経過してからになるでしょうし、実際に服役するのはもっと先になるでしょう。
現状まだまだ実例がない状況ですので、今後先述した課題をクリアして適切に運用されていくかを見守っていく必要があります。
刑法改正に伴って導入された拘禁刑について刑事事件に精通した弁護士が解説します⑥
1 はじめに
今回の記事では拘禁刑の導入に伴って生じ得る刑務所の管理運営体制の変化について2回に分けて解説させていただきます。
拘禁刑の導入により、刑務所の管理運営体制にも変化が生じます。
具体的には①刑務所内の組織編成や役割分担の変化や②刑務官の役割や目的意識の変化が生じることが予定されています。
2 刑務所内の組織編成や役割分担の変化について
まず、受刑者処遇の個別化に対応するために、刑務所内の組織編成や職員の役割分担が見直されています。
法務省は「矯正改革推進プロジェクト」の中で、拘禁刑の施行を見据え、刑務官(看守)と教育・心理・福祉の専門職員がチームを組んで処遇を行う『チーム処遇』の確立を進める方針を示しました。
従来、刑務官は主に保安警備や規律維持を担当し、教師やカウンセラーが別途指導を行う形でしたが、今後は複数の職種が一丸となって受刑者の改善更生を支援する体制に移行します。
例えば、あるモデル事業では刑務官、法務教官(教育専門官)、心理技官、福祉専門官(社会福祉士)、作業療法士、看護師といった多職種チームを編成し、受刑者ごとに処遇・支援計画を策定して定期的に見直す取り組みが行われています。
これにより、拘禁刑下では受刑者の問題状況を多角的に把握し、適切な処遇プログラムを提供できるようになると期待されています。
3 刑務官の役割や目的意識の変化
刑務官の役割も大きく意識転換が求められます。従来は規律違反の取り締まりや作業の監督が中心でしたが、これからは受刑者の良き指導者・支援者としての側面が重視されます。
チーム処遇の一員として、刑務官も受刑者の更生プランの策定や面談に関わり、日常生活全般の指導を行います。そのための研修強化や人員配置の見直しも進められています。
人権意識の向上やコミュニケーション技能の研修はもちろん、専門職との連携を円滑にするための体制整備が行われています。
一方で、保安担当と処遇担当を分離すべきとの意見もあり(過去の刑務所職員による暴行事件の反省から)、現場では模索が続いています。
いずれにせよ、刑務官が単に管理する存在から、更生を支援するパートナーへと役割がシフトしていく流れは確実であり、その意識改革が刑務所運営の鍵を握るでしょう。
しかし、当然ながら、多様な処遇プログラムの実施や刑務官の役割が変化することに伴って、必要な人材の確保や専門性の確立、十分な施設環境の整備が間に合うかという課題も指摘されています。
そこで次回の記事では、拘禁刑導入に伴う施設環境の改善や、予想される現場の負担とその対応についてさらに詳しく解説していきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では拘禁刑が導入される前から、刑罰を受けた方の立ち直りの支援、再犯を防止して真の更生を図ることに力を入れてきました。今後も事件を起こされた方の更生支援、再犯防止に全力を注いでいきます。更生支援や再犯防止、早期の仮釈放に向けた支援に興味のある方は自費こちらからお問い合わせください。相談は初回無料で対応させていただきます。
« Older Entries




