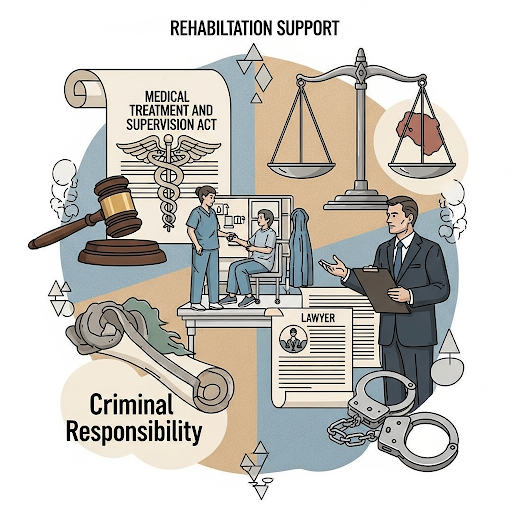
【事例】
Aさんは、佐賀県鳥栖市で60代の両親と一緒に住む40歳の男性です。
以前からAさんは精神科に通院しており、統合失調症であるという診断を受けていました。
これまでは家族に支えられながら日常生活を営んできたAさんでしたが、あるときから統合失調症の影響で幻覚や幻聴に悩まされるようになってしまいました。
その幻覚や幻聴は、「毎朝自宅に新聞を届けに来る新聞配達員は自分たち家族の命を狙っている」、「このままでは自分や家族の命が危ない」といったものでした。
このような幻聴と幻聴に囚われたAさんは、ある日、朝刊の配達に来た新聞配達員にカッターナイフで切りかかってしまいました。
異変を感じて駆け付けた人々がAさんを取り押さえたため、新聞配達員は怪我を負ったものの、命に別状はありませんでした。
その後、駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
逮捕されたAさんは警察の取調べを受けるとともに、Aさんに刑事責任を問えるのか判断するため、医師の鑑定も受けることになりました。
Aさんの家族は、Aさんの弁護人である弁護士から、担当の検察官は、医師の鑑定の結果を踏まえて、Aさんには刑事責任を問えないと判断して不起訴とする予定だと聞かされました。
もっとも、今後は医療観察法の手続きを受けることにもなるとも伝えられました。
Aさんの家族は、これからAさんがどのような手続きを受けるのか、Aさんが家に帰ってくることができるのかなどが心配となり、担当の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
このページの目次
1 はじめに
今回の記事では、Aさんがどのような手続きを受けることになるのか、医療観察法の手続きとはどのようなものなのかを説明するために、その前提として、まずはAさんに刑事責任を問えない理由を解説していきます。
2 責任能力とは
ある人が行った行為を、犯罪であるとして刑罰を科すためにはいくつか条件があります。
その一つが責任能力です。
責任能力というのは、ある行為を行った人を非難するために、その行為を行った人に必要とされる一定の能力です。
このような責任能力がない場合としては、心神喪失(刑法39条1項)と言われる場合と、刑事未成年の場合があります。
刑事未成年というのは、14歳未満であることです(刑法41条)。
このいずれかに該当するのであれば、例え人を殴った、人の物を盗んだといった犯罪に当たりうる行為をしていたとしても、責任能力がないため、犯罪とはなりません。
3 心神喪失とは
それでは、心神喪失とはどのような場合でしょうか。
これは、ごく簡単に表現すると、精神の障害(病気など)により、自分の行為がしていい行為かどうか、良い行為か悪い行為かを判断する能力か、その判断に基づいて自分の行動をコントロールする能力のいずれかが全くない状態を指します。
これに対して、こういった能力が全くないわけではないが、著しく減退した状態を心神耗弱(刑法39条2項)といいますが、この場合は(限定的ではあるけれども)責任能力はあるので、犯罪は成立することになります。
Aさんの場合は、担当の検察官はAさんの刑事責任を問えないと判断していますので、医師の鑑定の結果などを踏まえて、Aさんは心神喪失であったと判断したのでしょう。
そのため、刑事裁判にはかけられませんから、不起訴と判断したものと思われます。
次回の記事では、医療観察法の手続きについて解説していきます。
責任能力が問題となりうる事件で逮捕された場合、発達障害などの診断を受けている方が刑事事件を起こし逮捕された場合には、まずは弁護士を留置先の警察署に派遣する初回接見サービスの利用をおすすめします。責任能力が問題になる場合の弁護活動についてはこちらのページも参考にしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関わってきた経験を活かし、刑事事件後の再犯防止に向けたサポートにも力を入れています。
再犯防止に向けた弁護士のサポートにご興味のある方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。





